| 安全登山楽講 | |
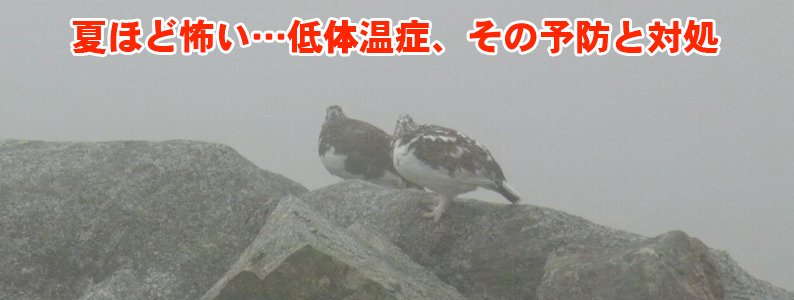 |
|
| 高山で登山者が動けなくなったときは、低体温症を疑ってみる必要がある。 |
| 安全登山楽講 | |
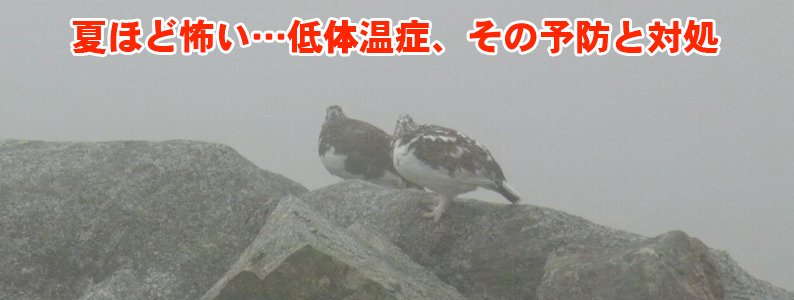 |
|
| 高山で登山者が動けなくなったときは、低体温症を疑ってみる必要がある。 |
| 意外と多い低体温症…しかしその病名は案外聞こえてこない。 |
| やまたび倶楽部の槍ヶ岳登山において肩の小屋から穂先を往復する間に同行者をサポートしていたサブリーダーが低体温症にかかり、小屋に戻った後、苦痛の4~5時間おくることになった。小屋だから暖もとれ、お湯もふんだんにあったので、暖かい部屋に横にさせ、温かいココアを飲ませ、ペットボトルにお湯を入れ湯たんぽにして体をあたためて事なきを得たが、テント泊だったらと思うと『ぞーっ』とする。 私自身、沢登りが好きで春・夏・秋と沢に入るが、真夏の谷でも低体温症の危険を感じることが多々ある。厳冬期はもちろん、春や秋、夏山という無雪期でさえも、登山者は、山のはげしい気象条件のなかにさらされていることを知っておかなければならない。ひとたび体温が下がると、たしかな歩行はおろか、思考力も弱まり、結果、致命的な事故につながっているのが実情である。近年、ブームともよべるほど登山がさかんになり、中高年を中心とした登山者が急増。それにつれて、山での遭難事故も増加している。 日本において、今や登山は観光旅行の延長や日常的なレジャーとなっているのか軽装備で入山した登山者が、山での寒気に対応できず低体温症におちいり遭難、さらには死亡する事故があとを絶たない。 1999年4月に浅間山で4人、9月に羊蹄山で2人が「低体温症のために亡くなった…」との報道は、私自身、低体温症という病名について初めて認識した山岳遭難事故のように記憶している。それまでは寒い山で死亡したら、死亡原因は『凍死』として報道されていたように思う。約20年前になるが1989年10月8日、立山で10人の中高年パーティが遭難し、そのうち8人が死亡した事故は低体温症による山岳遭難の典型的なケースと思われる。 |
| 低体温症とはなにか |
| 哺乳動物である人間は、気温など外の環境が変化しても体温をほぼ一定に保つことができる。この体温のコントロールは、人の意識とは無関係に脳の体温調節中枢が中心となって生理的におこなわれている。しかし、気温の低下などで体から失われる熱の量が、運動によって体がつくり出す熱の量を上回り、人体の生理的な体温調節の能力を超えると、体温は低下していく。 人間は衣服を身につけたり、住居の暖房をするなどして寒気から身を守り体温の低下を意識的に防いでいる。寒気がきびしいときに、意識的に体温の低下を防ぐ手段を講じないと、人の体温(厳密にいえば、深部温度)は低下し、体にさまざまな病的状態をひきおこす、これが低体温症である。 世界的にみれば、寒気などの低温が人体にどのような影響を及ぼすかの研究は、1953年のイギリスのエベレスト登山隊に加わったグリフイス・ヒユーによって始まったといってもよい。ピユーは高所医学への大いなる貢献者として知られているが、低体温症の研究においても、彼のはたした役割は大きい。 さらに、64年、嵐のなかで開かれた登山競技で3人が死亡し4人が重態になったことをきっかけに、グリフイス・ピユーをはじめ多くの研究者がさらに研究を進め、低体温症の概念が確立された。 いっぽう、アメリカでもウイルカースンらが低体温症の研究を進め、その成果は85年に出版された『Hypothermia,Frostbite and other Cold Injuries』としてまとめられた。この本は欧米の登山者にとって低体温症に関するバイブルのような存在で、出版されてから10年以上たった今日でも古さをまったく感じさせていない。この項で多く記載している事項の多くは、本書によっていることをあらかじめ申し添えておきたい。 |
| 体温は、どのようにして低下するのか。そのメカニズムは | ||
| 熱は対流・伝導・蒸発・放射の4つの方法で人から失われる。 | ||
| 対 流 | 対流による熱の喪失は、体温より低い温度の空気や水がつぎつぎに入れかわって皮膚に接触する際におこる。寒い野外で風が吹いていると、熱は主として対流によって失われる。 その量は風速の2乗に比例する、つまり風速3mの風が6m、9mと吹き、2倍、3倍になると熱の失われる量はそれぞれ4倍、9倍へと急速に増加し、とてつもない値に達する。この現象は「風冷え」とよばれている。 |
|
| 伝 導 | 伝導は、体と直接接触している物質に熱エネルギーが移る屯象をさしている。空気は伝導によって熱を伝えにくいが、水は伝導率が高い。地面も比熱の高い伝導体なので、けがをしたり体調がわるくて雪の上や地面の上に横になると、熱は体から大量に失われる。 | |
| 蒸 発 | 蒸発は、水が水蒸気になる現象だが、その際に気化熱を奪う。人体は汗をかくことによって熱が失われるので、濡れた衣脹を着ていると、蒸発と伝導によって大量の熱が失われる。 | |
| 放 射 | 放射は、熱を放出したり吸収する現象で、人体は自分より温度の低い近くの固体に常に熱を放射している。太陽や火の熱は放射エネルギーによって人を暖める。 | |
| ●深部温度 core temperatureとは、体表面から2.5cmより内側の、温度がほぼ一定しているところをさす。これが、蕨密な意味での体温である。 | ||
| 低体温症の症状 | |
| 通常の体温計は摂氏34度以下の体温を測定できないので、低体温症の程度は訴えや症状から判断せざるをえない。 | |
| ① | 寒気にさらされると体温が低下する前に、手や足の皮膚の温度が低下して知覚神経の感覚がにぶくなり、しびれた感じがしたり、口のまわりの筋肉がこわばって、ろれつがまわらなくなる。 |
| ② | 低体温症に陥り始めると、まず歯の根が合わなくなり、寒いと感じふるえることが多い。ふるえは、自分の意志とは無関係な筋肉のけいれんによって体が必死に熱をつくりだし、低下した体温をもとにもどそうとしていることを意味し、低体温症への警告のサインとして重要である。 |
| ③ | そのほかの初期の症状としては、靴のひもをしめたり、ライターの火をつける、服のファスナーを閉めるといった手の細かい作業ができなくなったり、あたかも子どもがぐずっているような、ふだんの行動からは考えられない態度をとるようになる。 |
| ④ | さらに体温が低下すると、なんでもないところでよろめいたり、つまづいたりしはじめる。 |
| ⑤ | 体温が摂氏32度以下に低下した重症の低体温症では、ふるえが止まり、歩くどころか立っていることもむずかしくなる。精神活動に変調をきたし、寒さから身を守ることにまったく無関心になり、手袋をつけなかったり、上着のファスナーをしめ忘れてしまう。逆に、衣服を次から次へと脱いでしまうことさえある(逆説的な脱衣)。 |
| ⑥ | ⑤このような状態から、さらに意識のレベルが低下し、もうろう状態から昏睡状態におちいる。 |
| 低体温症の初期の症状は疲れた時の症状に非常によく似ているため、つい単なる疲労と考えがちである。雨まじりの風が吹き、体がすっかりぬれているときには、とりわけ低体温症を強く疑わなければならない。 | |
| 低体温症の予防 | |
| 低体温症は予防が大切である。寒気のなかで防寒が不充分だと、人は短時間のうちに低体温症になるが、野外で、いったん低下した体温をもとにもどすのはきわめてむずかしい。 人が熱を失なう対流、伝導、蒸発および放射の4つの方法を理解していれば、失なう熱をできるかぎり少なくする手だてをうつことができるが、その中心となるのはウェアリングである。充分な衣服を着ていないと、それこそ走るようなペ-スで歩き、大量の熱をつ〈り出さなければ、体から失われる熱をおぎなうことはできない。それは通常の登山者にとっては不可能なことである。したがって低体温症になるのを防ぐには、防寒性の高い衣服を着ていることがまず基本である。 |
|
| ●ウェアリング | |
| 蒸発と伝導による熱の喪失を防ぐには、水分をため込んでしまう衣類を着ないことがまず大切である。綿素材は、汗や雨などで外からしみこんできた水分をそのまま吸収してすっかりぬれてしまうので、登山の際の衣服としてはきわめて不適切である。その点、ウールは水を吸い込みにくく、繊維のあいだに動かない空気の孔が無数にあるので、蒸発と伝導によって熱が失われにくく断熱効果が高い。ウールのセーターは登山の際、必ず持っていくべきだろう。現在では化学繊維でもウールに劣らないものが多くある。 また、風が吹いていると対流によって大量の熱が奪われるので、風を通さず、水がなかにしみこまない衣服をいちばん外に着る必要がある。 放射による熱の喪失を防げる有効な衣服はほとんどないが、放射による熱の喪失は、対流や伝導、蒸発によるものとくらべれぱ少ない。 |
|
| ウェアを選択して快適かつ安全な登山をしてください。 | ||||
 |
 |
 |
 |
 |
| 肌着 | 山シャツ | ベスト | ラガーシャツ | パンツ |
 |
 |
 |
 |
 |
| フリース | アウターシェル | ウインドウブレーカー | ウインドウブレーカー | レインギア(上) |
 |
 |
 |
 |
 |
| レインギア(下) | ソックス | 手袋 | オーバー手袋 | 帽子 |
| モンベル製品の一部をラインナップしました。多くのメーカーより販売されていますので登山用具店でご覧ください。 | ||||
|
|
|||
| ●食料 | |||
| 低体温症を予防するには、体が熱をつくり出すもとになる脂肪を燃焼させてエネルギーに変えることが大切である。そのためには、そのためには炭水化物を多く含む充分な食料を持っていかなくてはならない。 「ごはん」「パン」「スパゲティー」「うどん」「石焼いも」「フライドポテト」などが炭水化物を多く含む食物である。穀類や、芋類には炭水化物が多くふくまれる。 行動中もキャンディなどをたえず口に入れ、食べていることも寒気のきびしいなかでの登山では有効である。 |
 |
||
|
|
|||
| ●その他の装備 |  |
||
| ウレタンマットは、休息するとき、この上に座ることによって、伝導により熱が直接地面や雪へと失われるのを防ぐことができる。 ビバークする際には特に有用である。ツエルトは、やむをえずビパークする際、風をかなり避けることができ、対流による熱の喪失を減らすことができる。エマージェンシーブランケットは、重量が100g足らず、コンパクトで手のひらに入る大きさで熱の放射を80%遮断できる。いざというときに体をこれで包めば低体温症の進行を遅らせることができる。 |
|||
| 低体温症の対処法 | |
| ●軽症の場合 パーティの場合には、まずだれか一人が低体温症の症状を示すことが多い。その場合、安易に疲れていると判断せず、ほかのメンバーも低体温症になる危険が高いと考えて、予備の衣服があれば、ぬれた衣服と着がえて、ただちに下山を開始しなければならない。 すぐ近くに山小屋があればそこへ避難すればよい。野外では、たとえ温かい飲み物を飲んでも、気分は多少落ちつくが、体温を上昇させることはできない。冬山では、下山は必ずしも容易ではないので、稜線より下がって雪洞を掘ることである。 風を避けることができ、食料と燃料が充分あれば寒気をしのげ、体温は上昇してくる。 |
  |
| ●重症の場合 立つこともできず、意識がもうろうとしている重症の低体温症の場合には、稜線から下がって風を避け、テントやツエルトがあれば張って、急ごしらえのシェルターを作ることはできるが、体温を上昇させることのできるほどの効果は少ない。もっとも近い山小屋はどこにあるのかを冷静に考えて元気なものが助けを求めに行かなくてはならない。 重症の低体温症の患者の心臓は、体温の低下が進むなかで脈がだんだん遅くなり、最終的に停止するが、助け出してから治療をするなかで、乱暴に扱うと、突然、心室細動をおこして死亡してしまう。 |
 |
| したがって、首の骨が折れた患者を扱うように細心の注意を払って扱わなければならない。毛布などを何枚もそっと上からかけて、きわめて慎重に運び、けっして背中に背負って運んではならない。また、室内やテント内に運びこんだあと、間違っても、衣服を脱がして全身をマッサージするなどの手荒なことをしてはいけない。また、病院以外では急速に加温してはならない。 しかし、意識がまったくなく、一見死亡しているように見える場合にも、簡単に死亡していると判断してはならない。ゆっくり加温して体温を上げることができれば助かる可能性が充分あるからである。 |
|
| ※心室細動とは、心筋が同調性を失なって、ぼらばらに収縮し、心臓から血液が体に送り出されない状態。 | |
| 1989年10月の立山遭難の検証から | |
| これは、平均年齢55・5歳という中高年グループが、紅葉を楽しみに立山から剱をめざし、10人中8人が遭難死したという事故である。秋山への認識不足からおこったと考えられるこの遭難を、低体温症という観点から検証してみる。 室堂平から一ノ越を経て立山の雄山(3003m)まで標高差約600m、疲労困憊するようなルートではない。やまたび倶楽部でも2007年の8月と2008年5月に同ルートを山行している。 当日の室堂平の気温は摂氏零下6℃、この時は、ほぼ無風だったが、出発してまもなく雪が降り始め、まもなく吹雪になった。一行は綿の下着、スポーツシャツ、ベスト、ダウンジャケットなどを身につけていたが、6人はセーターを着ておらず、ウェアリングとしてはきわめて不充分であった。 雄山の山項で昼食をとったときにメンバーのひとりが足のしびれを訴えたため、「引き返そうか、どうしようか」と相談をしている。この時点で下山の決断をすべきだったと考えられる。 昼すぎに雄山から大汝山、富士ノ折立へと縦走を開始したが、午後3時半ごろには風速10mの吹雪となり、近くの山小屋の記録では、気温は摂氏零下10℃まで低下している。 この時にはすでに、抱きかかえないと歩けないメンバーが出ており、午後4時半ごろには、ひとりはすでに意識がもうろろうとしていたという。 約4時間程の短時間のあいだに重症の低体温症におちいってしまっている。吹雪のなかで、パーティはすでに寒さから身を守る理性的な判断能力が低下していた。リュックの中には着ないままのセーターが残っていたり、稜線から下がってハイマツ帯のなかで風と寒さを防ぎ、ひと晩をなんとかしのぐこともせず、8人は稜線上で倒れていた。 発見されたときに8人のうちの少なくとも一人はもうろう状態ながらまだ意識があったことから考えると、適切な処置をしていれば、何人かは生還できた可能性が残っていたのではないかと考えられる。 厳冬期には山での気温は摂氏0℃をはるかに下回り、軽装備で登山をおこなえば確実に低体温症になる。しかし、厳冬期に登山を行う登山者は充分な装備で山に入っている。 問題なのは春山と秋山である。この季節、平地ではもうだいぶ暖かくなった、まだ暖かい、といった春や秋の季節感のなかで人は過ごすが、山では気温が摂氏0℃を下回ることもめずらしくなく、気候が変わりやすく、強風が吹いたり、雨の降る可能性も高い。 雨は、雪に比べるとかえって衣服にしみこみやすく、体を冷やす危険性が高い。山ではまだ冬、もう冬なのだということを山に登る前にもう一度 |
| 再認識して、着ていく衣服や装備をしっかり点検して登山をおこなうべきであろう。 また、夏山でも3000m級の山では気温が低く、横なぐりの雨に打たれると、低体温症になっても少しも不思議ではない。 雨が降ったり強い風が吹いて天候が荒れ模様のときには、 |
 |
| たとえ登山口まで来ていても思いきって登山を中止する勇気が必要である。 まだ軽症のうちに低体温症だと気がつけば、登山の途中であっても、ためらわずにすみやかに下山を開始すべきである。 低体温症は予防がなによりも大切だということをあらためて強調しておきたい。 |
|
| 体温調節の要、レイヤードシステム | |
| ① | 快適かつ確実な登山を楽しむには、まず寒からず、暑からず、自身の体温を維持することが肝心。 |
| ② | 季節の変わり目は、服装にも迷うところだが、防寒と発汗の双方に配慮した服装を心がけたい。 |
| ③ | 一年中、重宝するのが、長袖のアンダーウェアである。 |
| ④ | 春山や秋山は、いつなんどき冬山のような天候に変わるかわからないし、また、夏山といえども、3000m級の稜線では、強風や雨などの悪天、夜のきぴしい冷え込みに見舞われることもある。 |
| ⑤ | 化学繊維のアンダーウェアは、速乾性や保温性、肌ざわりにすぐれ、さほど重量もないことから、生地の厚さや繊維の特徴を考慮し、山行シーズンに合わせたものを着用・携行したい。 |
| ⑥ | アンダーウェアの上には、遠乾性、保温性のあるアウターを着用し、さらに、防風性のあるものを用意する。春山や秋山の防寒着に関していえば、厚手のフリースなどを1枚用意するよりは、薄手のものを2枚用意したほうがよい。 これは、重ね着することで、乾いた暖かい空気の層をつくりだし、保温性を高めることができるからである。また、運動量が増え、暑くなった場合には、脱ぐことで微妙な体温調節ができる。 |
| ⑦ | レイヤードシステムを活用し、こまめに着脱して体温調節をすることが、疲労の軽減、しいては安全な登山につながる。 |
|
|
|||
| 中高年の安全登山を推進するために、栗栖 茜(くりす・あかね)先生の文献を引用させていただきました。 | |||
|
|
|||